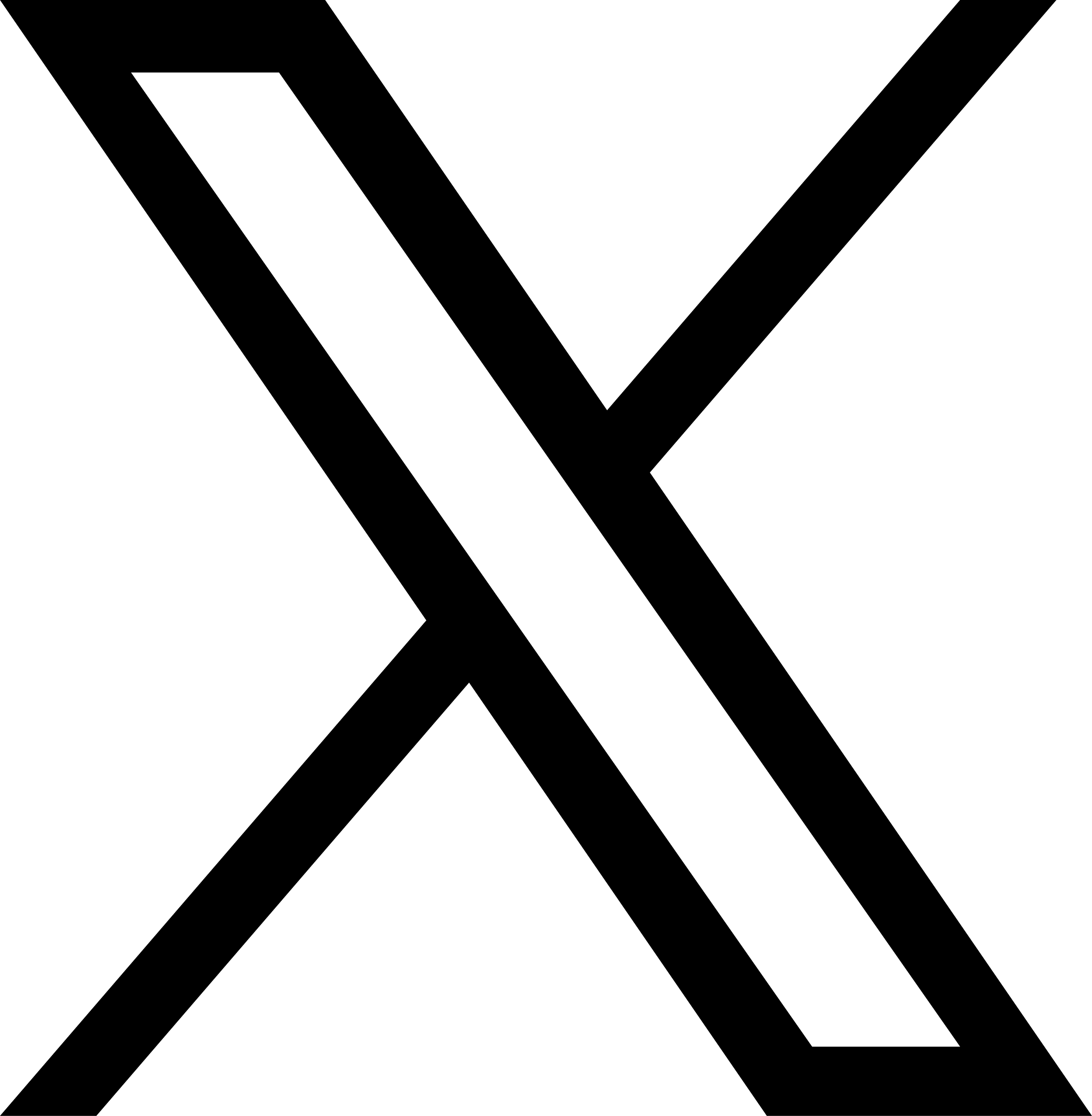地域での炭素耕作の実証
本拠点では、地域経済の活性化、持続的な発展に寄与することを目指します。
地域の課題を抽出し、それを解決するストーリーを「積み上げ型の環境デザインの構築」、それを「消費者に伝え、価値の理解を創出すること」により
組み立てることが肝要です。炭素耕作による持続的な発展の実現に向けて、生産・製造・流通そして消費者の連携が重要となります。
以下プロジェクトでの実証が、世界の課題解決に向けた先行事例として効果的であり、地球の未来設計図に貢献していきます。
西表島プロジェクト
本拠点は、ビジョンでも紹介したように、光合成のポテンシャルを最大限に活用する炭素耕作によるカーボンネガティブの限界に挑戦します。
特に稲作においては、メタン生成の抑制と二酸化炭素固定による寄与の他に、地域経済の活性化、持続的な発展を目指します。
本拠点では、この活動の場として西表島に注目しました。
西表島は “世界自然遺産”として認定されているため、環境に関連して数々の制約を受けます。本プロジェクトでは、農業、畜産、水産業、また流通や販売、ひいては島にとって重要な観光業にもつながる、資源循環、価値創造に向けた、拠点の技術の適用を狙います。
この活動での炭素耕作型稲作に関する研究には、以下の背景と課題があります。
- イネが、東南アジアで最も広く栽培されている作物である
- 稲作において、化学肥料や農薬の利用削減が重要な課題である
- 水田での稲作は、温室効果ガスであるメタンや亜酸化窒素の排出源となる
西表島が抱える課題
更に、具体的に西表島が抱える課題として、以下の事が挙げられます。
- 農畜水産物の地産地消の課題
島で生産される農畜水産物の多くが島内で消費されていません。その一方で、島外から流入しています。 - 化学肥料や農薬の使用の影響
農業は西表島の主要な産業であると同時に、自然環境において重要な役割を担っています。
しかし、化学肥料が海洋に流失することで富栄養化し珊瑚礁に影響を与えています。また、農薬による生物多様性への影響もあります。 - 牛糞の処理
牛糞の処理ができていないため、自然環境に影響を与えています。 - 生ごみ処理
島民や観光客により発生する生ごみの処理ができていないため、自然環境に影響を与えています。 - 海藻藻場の減少
海藻藻場が減少し、魚が獲れなくなっています。 - 海洋プラスチックゴミ
海岸に多くの海洋プラスチックゴミが漂着しており、処理ができず、景観だけでなく自然環境にも大きな影響を与えています。
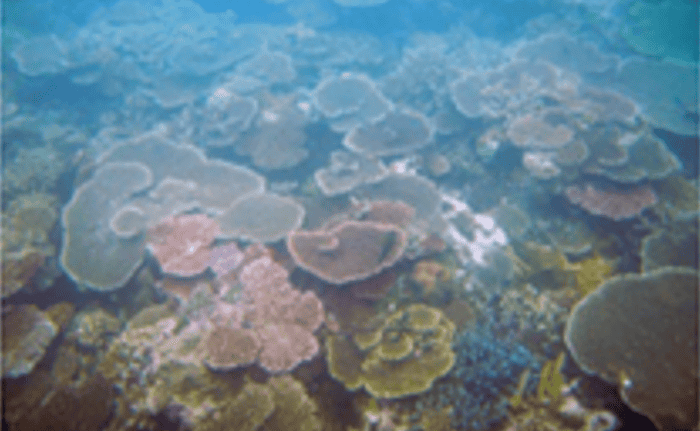



本拠点活動による様々なソリューションの創出
これらの課題に対して、我々は以下の活動で取り組みます。
- 地産地消の実現と新たな価値の創出
自治体や地元の企業(ホテルなど)と連携して地産地消を実現します。
また、世界自然遺産としての価値を生かした西表島の農産物の新たな価値を創出します。 - 島嶼型循環農業システムの開発
農業・畜産廃棄物および生ごみの堆肥化などによる島嶼型循環農業システムを構築し、化学肥料を使用しない有機農業の実現を目指します。 - 炭素耕作型稲作
新たな価値創出を可能とする稲を開発すると同時に無農薬を実現するための炭素耕作型稲作技術を創出します。 - 海草藻場の再生
藻類を用いた炭素耕作で開発する技術を利用して海藻藻場の再生を目指します。 - 本拠点の技術を用いた多様な課題への挑戦
本拠点のメンバーが有する様々な技術を利用して、西表島の様々な課題に挑戦します。
特に項目1についての具体的な計画は、島での米の安定した生産、収量の向上を目指す技術導入、地産地消を目指した酒(泡盛)の生産、および流通においてその価値が消費者にも認められる社会の形成を目指すものです。西表島には酒造メーカーは無く、本プロジェクトでは泡盛の生産は石垣島の高嶺酒造所にて行います。
2025年2月27日に、沖縄 西表島でシンポジウムを開催し、社会実装における課題解決に向けた連携パネルディスカッションを行いました。
シンポジウムでは、社会実装拠点横断型研究会を中心に、現地の課題も意識した社会実装連携について議論しました(シンポジウムの様子はこちら) 。